8.1 トランジスタの抵抗測定
表2の通り、抵抗値はE-B、C-B間で測定でき、それ以外では抵抗値を図ることができなかった。npn形トランジスタはベース端子にP形半導体、残り2つの端子にN形半導体が使われているので、電流はP形からN形にしか流れない。そのことからB-EとC-B、E-C、そしてC-E間では電流は流れないと考えられ、結果抵抗値が無限大になると考えられる。E-B、E-C間で抵抗値が測定できたのは順バイアスがかかり、電流が流れたためであるといえる。
8.2 グラフについて
まず、図6のグラフだが、パラメータであるIbが大きくなるにつれてコレクタ電流が大きくなっていることがわかる。これはトランジスタがE-B間に電流が流れると、E-C間にその何倍もの電流を流す(増幅作用)があることを示している。また、飽和電圧Vce(sat)はIbが大きくなるにつれて大きくなっている。またこのグラフからわかるように、電流増幅率βは最大で約260になる。
図7のグラフは、概ねダイオードの特性に似ており、0.7[V]辺りから電流が流れ始めてい。E-B間は順バイアスをかけて動作させるので、特性は通常のPN接合形ダイオードと同じになると言える。当然、Vceの殆どはC-E間の空乏層にかかるので、Vbe-Ib特性に関与することはまずない。
図8において、IcとIbは比例関係にあるといえる。トランジスタがベース電流でコレクタ電流を制御するという観点から見ると、これは理にかなっているといえる。またこのグラフからβを求めることが出来る。βはIc/Ibで求められ、またそれはこのグラフにおいて傾きを表すものである。このグラフからβを求めると260前後になり、図6のグラフから求めたものと一致する。
図9で、ベース接地ではIcはVcbによらず一定であることがわかる。またIcの大きさはこのグラフでパラメータにしたIeによって決定されることがわかる。
図10で、Veb-Ie特性はやはりダイオードの特性に近くなるが、Vcbによってその値が変化することがわかる。立ち上がり電圧はVcbによって変化する。実験の途中で抵抗器から煙が出るトラブルがあったため、Vcb=6[V]のときのデータが正しく取れていない可能性がある。
図11では、図9からもわかるようにIcはVcbに関わらず一定で、IcとIbは比例関係にあると言える。このグラフの傾きがαであると言え、その値は常に1以下を保っている。
図12は図7に電圧補正を加えたものである。
8.3 増幅率αとβについて
βは前述のとおり、260前後である。αはβ/(β+1)で表されるので、実際に求めたβを入れてみると、0.996169…となったので、ほぼ1であると言える。これは図11より求められるαと概ね合っている。
8.4 入力抵抗と出力抵抗の検討
図6、図9より出力抵抗を、図7、図10より入力抵抗をそれぞれ求める。
・入力抵抗
エミッタ接地:2034[Ω]
ベース接地:4.06[Ω]
・出力抵抗
エミッタ接地:25000[Ω](Ib=20[μA])、10000[Ω](Ib=40[μA])、1250[Ω](Ib=100[μA])
ベース接地:∞
エミッタ接地の入力抵抗は、概ね出力抵抗より小さく、またエミッタ接地の出力抵抗はIbが増加すると減少することがわかる。
ベース接地においては、入力抵抗は低く、出力抵抗に至っては抵抗は∞になった。
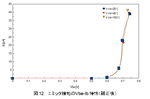
あ、はい。
何故このグラフだけ貼り付けた?
何を言っているのか理解しかねますな。
 [0回]
[0回]
PR
